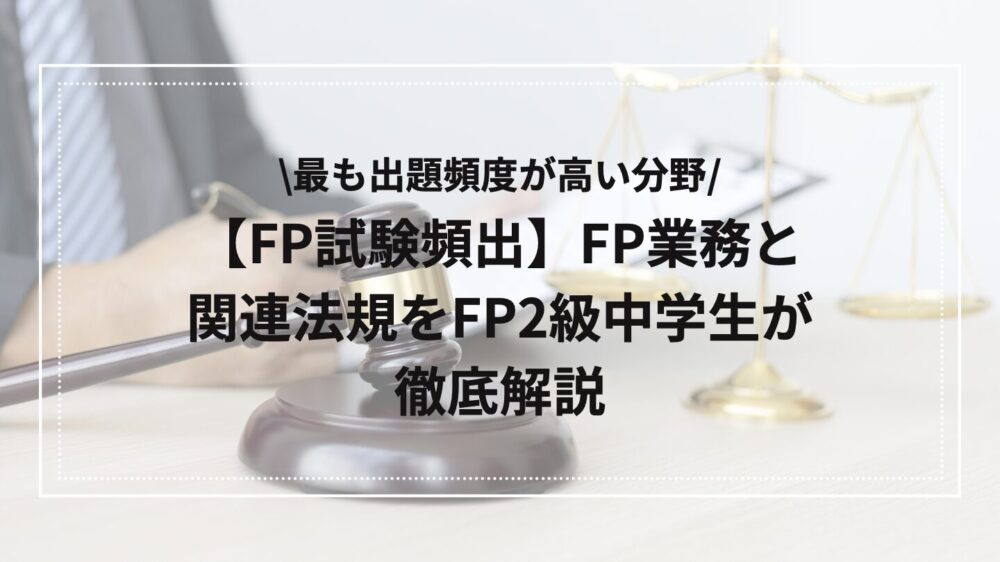FP試験で最も出題頻度が高い分野、「FP業務と関連法規」。
この分野では「FPにできること・できないこと」や「守るべき職業倫理」が問われます。
この記事では、FP試験によく出る関連法規のポイントを整理しつつ、FP2級を中学生で合格した僕の学習経験も交えて解説していきます。この分野を徹底的に抑え、FP試験合格に近づけましょう。
FPの職業的原則
FPには「顧客の利益を第一に考える義務」があります。試験では次の原則を基本として問題が出題されます。
- 顧客本位:顧客の利益を優先する(FP自身の利益を優先してはいけない)
- 秘密保持:顧客の個人情報は絶対に守る
- 公正中立:特定の金融機関や商品に偏らない助言を行う
- 継続的研鑽:FPは常に知識をアップデートし続ける
この4つは覚えるというより普通に考えて常識なので、あんま気にしなくても大丈夫です。この先の関連法規もこの4つを軸に考えれば解けます。なのでこの分野はラッキー問題ですね。笑
FPと関連法規のポイント整理
金融商品取引法
- 適合性の原則:顧客に合わない商品を勧めてはいけない
- 説明義務:リスクや手数料はきちんと説明する必要あり
👉 僕が問題演習をしていて一番よく見たのは「FPは投資判断の助言や顧客の資産運用を行なってよいか?」という問いです。答えはもちろんしちゃダメです。
保険業法
- 保険募集はFP資格だけではできない(保険会社の募集人資格が必要)
- 重要事項説明や告知義務がポイント
👉 FPの勉強をする前は「FPなら保険を売れるのかな」と思っていましたが、実際は違いました。FPは保険の仕組みを説明できても、販売は「保険募集人」にしかできません。
税理士法
- 税務代理(確定申告の代行)は税理士のみ可能
- FPができるのは「一般的な税制の説明」まで
👉 この分野は全て頻出ですがここは特に出やすい印象です。
実際の過去問でも「FPが顧客に代わって確定申告を提出するのは正しいか?」といった問題が繰り返し出題されています。
宅地建物取引業法
- 不動産の仲介や契約行為は宅建士のみ可能
- FPは「住宅ローンの資金計画」などアドバイスにとどまる
👉 不動産はFP試験でも大きなテーマ。なのでここもしっかりおさえておきましょう。
弁護士法・司法書士法
- 法律相談や裁判代理は弁護士の独占業務
- 登記申請は司法書士の業務
- FPは一般的な制度説明にとどまる
FP試験で狙われる問題パターン
- 「FPが顧客に代わって登記を行う」 → ✕(司法書士業務)
- 「FPが一般的な税制の仕組みを説明する」 → ○
- 「FPが保険契約の募集を行う」 → ✕(保険募集人が必要)
- 「FPがライフプラン作成のために税制の基本を説明する」 → ○
この分野は一般的ときたらできる、専門的ときたらできないというケーズがほとんどです。そこを意識して解くと正答率が上がるかもしれません。
僕が思うFPと関連法規の大切さ
正直、最初に勉強しているときは「ただの暗記分野だな」と思っていました。
でも学んでいくうちに、FPが何でもやっていいわけじゃないという当たり前のことを理解できました。
FPはライフプランを立てるときに、税金・保険・不動産・投資など幅広い知識を使います。
でも実際の手続きは、それぞれの専門家がやる。
FPは「顧客の人生に寄り添い、必要に応じて専門家につなげるハブの役割」を持っているんだと気づきました。
試験的には暗記で得点源にできますが、実務的にもすごく大事な分野だと思います。
まとめ
- 職業的原則を軸に問題を解く
- 一般的というワードをおさえると正答率UP↑
- FPの役割は「顧客に寄り添い、必要なときに専門家へつなぐこと」
僕はFPを勉強して、この分野を学んで一番「FPって万能じゃないんだ」と気づきました。
でもだからこそ、顧客本位で中立的にサポートできるのがFPの強みだと思います。試験対策としてはもちろん、実際にFPとして活動するためにも、この分野はしっかり理解しておきたいですね。
この記事が少しでも役に立ったら嬉しいです。これからもFP試験の有益な知識やお金の知識を発信していくので他の記事もぜひ見てみて下さい。ありがとうございました。